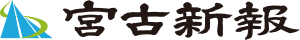つなぎびと「宮古島を愛する先にあるもの」
「島には何も無い」「都会は最先端なものが集まっているから、若いうちに島から出た方が良い」
様々な場面でそう聞いて育った私は、その言葉を疑うことなく、島外ばかりに目を向けていた。そんな私の視野が宮古島へ向くようになったきっかけが、宮古島市役所に勤める三上暁さん(42)の存在だ。
三上さんは島育ちの私が足元にも及ばないほど宮古島を愛し、住民に目を向けている。その地域愛の原点は、東京にあるニュータウンに住んでいた幼少期まで遡る。住民の多くは地方からの移住者で、多様な文化が交わり合う場所だったが、その土地に根ざし、受け継がれた文化や歴史は無かった。
いつからか、それらを持つ地域へ強い憧れを抱いた三上さんは、大学では文化人類学を専攻し、研究に励んだ。
三上さんと沖縄の縁は小学生の頃、ハレー彗星を観察するために家族で訪れた久米島から始まる。それから何度も足を運び、沖縄での生活を志した三上さんは、就職先を念願の沖縄で果たす。その就職先が宮古島市役所だった。
知り合いの居ない場所で、三上さんは島に根付くものを全身で吸収すべく、導かれるまま地域に入っていった。お祝いの席へ参加し、オトーリの洗礼を受けたり、地元の野球チームへ所属して汗を流したりもした。文化や風習を知り、島民と繋がるたびに、宮古島に魅了されていった。
「宮古島には、家族のような存在の方々がたくさんいるんです」と三上さんは嬉しそうに語る。
地域に溶け込み、島民と接する中で「世間の当たり前や、都会の基準にただ流されるのではなく、宮古島らしさを大事にした上で行動できないか」との問いが芽生えた。その問いは、現在務める市役所で働く上での軸になっている。
「便利さが全てなのか、宮古島らしさとは何なのか」、三上さんの言葉は島民の心を揺さぶる。対話にこそ答えがあると信じ、時間をかけて島民の真意を掘り起こす。当たり前すぎて見過ごしがちな地域の価値は、時として「不要」と判断される。しかし、三上さんのように地域と心から向き合い、判断に「待った」をかけることで、数十年、数百年先に宮古島らしさがいつまでも生き続けることができる。
「宮古島の為に、何ができるのか」、三上さんの使命感は島民との交流を通じて日々深化を増す。(執筆・ピコパル/隔週日曜日掲載)