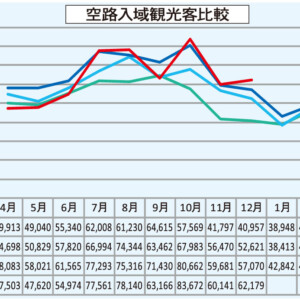うむい紡ぎてぃ言葉守らでぃ みゃーくふつ継ぐ語りと歌声 保存継承へ講演、合唱
市文化協会(饒平名和枝会長)は13日、未来創造センターで2025年度宮古方言保存継承事業「シンポジウム~みゃーくふつをつなぐため~」を開催した。同協会が4年間かけて取り組む同事業の一環で、今回がそのキックオフ。会場には宮古方言に関心を持つ多くの市民が来場し、基調講演や民謡解説、座談会を通じて言葉の魅力と継承の可能性を模索し、共に考える機会とした。

基調講演「みゃーくふつの魅力と継承の可能性」では、国立国語研究所特任助教のセリック・ケナン氏が登壇。大正期に来島したロシア人研究者ネフスキーが残した「宮古方言ノート」を紹介し、みゃーくふつが日本語と同系統に属しつつ独自の体系を持つ点を解説した。
それによるとみゃーくふつの特徴として、独自の発音体系や時間表現の多様さがあり、未来を示す場合に「~がまた」「~でい」を必ず使い分ける仕組みを例示し、日本語にない精緻さを持つと説明した。一方で、教材不足や学習環境の課題も挙げ「十代を過ぎると習得は難しくなる」と警鐘を鳴らし、「保存と普及は日本語史を理解する上でも重要」と説明した。
宮古民謡保存協会による「まーつき宮古民謡」では、「豊年の歌」を披露し、来場者が手拍子を合わせて合唱。砂川美佐子副会長が歌詞の背景について説明し、生活文化や自然との結び付きを示した。
座談会では、教育現場や地域活動に携わる関係者と参加者が課題と展望を語り合い、保存の具体策を探った。
冒頭あいさつした饒平名会長は「ユネスコから消滅危機言語とされたミャークフツの保存・継承は喫緊の課題。今回の催しが未来を考える契機になれば」と述べた。
同協会は今後4年間で「改訂版宮古方言ノート」を刊行し、最終年度は出前講座などを実施する予定で、地域ぐるみの継承活動が進められる。