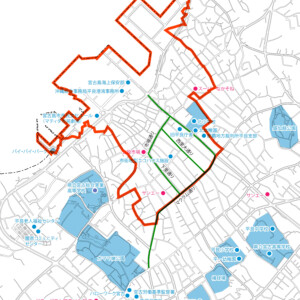「豊年のあやぐ」を神前奉納する亀浜さん
=宮古神社
向こう一年の実りへ祈年祭 宮古神社 玉串、踊り奉納し豊穣・豊漁を
宮古神社で17日、例大祭(6月)や新嘗(にいなめ)祭(11月)に並ぶ三大祭の一つ、「祈念祭」が厳かに執り行われ、参列者が奉納踊りなどを通して1年間の五穀豊穣を祈願した。
祈年祭は午前10時から始まり、辻信彦禰宜が清め祓いや祝詞奏上などを執り行い、琉球舞踊穂花会家元の亀浜律子さんが「豊年のあやぐ」を神前奉納したほか、責任役員の砂川恵助さん、下地義治さんをはじめとする代表参列者が、神職から受け取った玉串を神前にかざし、1年間の五穀豊穣と豊漁を祈念した。
祭典を終えて辻信彦禰宜は参列者に「皆さんと1年間の島々、国々の発展を無事祈ることができてよかった」と安堵した様子。その上で「次回の新嘗祭や例大祭にも足を運んでほしい」と述べた。
毎年2月17日に行われる宮中祭祀の小祭「祈念祭」は「としごいのまつり」とも呼ばれる。「とし」とは穀物(特にお米の稔りの美称、「こい」は祈りや願いを意味し、春の耕作始めにあたり、五穀の豊かな稔りを祈念する神道の祭祀の一つだ。
天武天皇の頃の7世紀後半にはすでに記録もあり、農耕が生活の中心であった時代に稲の育成周期を日本人の一年として祈ることは国家の安泰、国民の繁栄を祈ることにあるとされた。
祈年祭が五穀豊穣を祈るお祭りであることに対し、新嘗祭は収穫に感謝するお祭りにあたる。