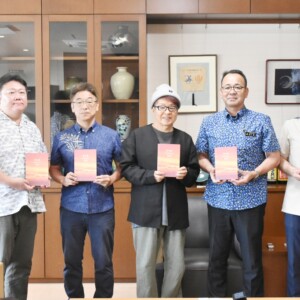良質な糸へ客観的評価 宮古上布保持団体主催 苧麻糸不足が共通課題
宮古上布保持団体(新里玲子代表)主催の「苧麻(ちょま)糸シンポジウム」が19日、下地農村環境改善センターで行われた。宮古上布や八重山上布、新潟県の小千谷縮・越後上布、福島県昭和村のからむし織の苧麻を原材料とする各産地連携のシンポジウム。基調講演や産地報告があり、座談会では苧麻糸不足の共通課題で意見を交えた。苧麻糸確保に向けては栽培技術のデータ蓄積の取り組みなど説明があり、良質な糸作りに向けては客観的な品質評価基準を設けることを改めて確認した。
同シンポジウムは情報共有や意見交換で知見を広げ、「糸績み技術者増加」への解決の糸口を探ることを狙いに開催された。
座談会では宮古上布保持団体代表の新里さんが進行役を務め、友利明美さん(宮古苧麻績み保存会長)、浦崎美由希さん(宮古織物事業協同組合代表理事)、新垣幸子さん(重要無形文化財「八重山上布」各個認定保持者)、根本崇範さん(福島県昭和村産業建設課からむし振興係長)、安達桂祐さん(新潟県小千谷市にぎわい交流課文化財係長)らが参加。原材料の苧麻糸や良質な糸の確保の課題解決に向けて意見を出し合った。
浦崎さんは「基本的には産地として糸を買っている。作り手から糸を受けて織り手につなげている。織物組合といっても昔ほど糸が入らないのが現状。買う時は評価を大事にしている」と現状を説明した。
新里さんは糸の品質で太さの緊密、毛羽、つなぎ方、撚りかけなど五角形グラフによる評価方法を提案した。
見解を求められた柳悦州さん(沖縄県立芸術大客員・名誉教授)は「織り手がどういう糸が欲しいのか、績み手はどういう糸を績みたいのを考え、それに客観的な条件を付けられるのかを考えて決めるのがいい」と助言。さらに「皆さんで考えることが課題で他の産地はどうなのか、他の素材ではどうなのかなどを研究し、突き詰めていくことが産地として求められている」と強調した。
仲間伸恵さん(琉球大学准教授)は「産地報告を聞き、それぞれが頑張っていることがよく分かった。(今後へ向け)関係者だけでなく一般の人も巻き込んでのネットワーク作りの話もあった」と島ぐるみの構築を呼びかけた。苧麻糸確保など課題には「簡単に解決することではないと思っていたが、皆が集まって課題を共有し動き出すことは良い」と評価した。
会場では宮古上布、手績み苧麻糸、八重山上布、小千谷縮・越後上布、からむし織の作品が展示されたほか「ブーンミの島」「からむしのこえ」も上映された。