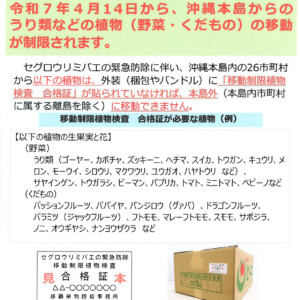総合博物館で深堀り 学芸員による展示解説 国際博物館の日 歴史・民俗の価値共有
2025年度「国際博物館の日」となった18日、市総合博物館は同日中は館内を無料開放し、学芸員による展示解説イベントを行った。同博物館学芸員の湯屋秀捷(ゆや・ひでとし)さんが参加者に館内を案内し、島内の御嶽やパーントゥなどの伝統祭祀、風葬や洗骨といった歴史および民俗に関する展示について詳しく解説。午前と午後に2回実施された。
この解説イベントは同博物館の2025年度国際博物館の日記念事業「んみゃーち、みゃーくんみゃーち博物館」の一環で実施されたもの。普段は研修や小中学生向けとして実施しているが、一般向けの解説は今年度初となった。
この日は入館も無料とあって訪れた市民らは展示品に興味深々だった。展示解説午前の部では約10人が参加し、湯屋さんの解説に耳を傾け、館内を巡りながら自然史、美術工芸、歴史・民俗などの各展示室など宮古島文化の奥深さに触れた。
解説では島の御嶽の数などについて説明。湯屋さんによると御嶽は800以上、祈願所を合わせると県内有数だという。
パーントゥについては終楽の繁栄を願ったりする行事であると説明。島で一番大きなムイカガーや湧き水について「宮古島の歴史を語る上で水は大きな関わりがある」と話したほか、仲宗根豊見親の持ち物だったとされる「金頭銀茎簪(きんとうぎんけいかんざし)」や人頭税など人と暮らしについても言及した。
湯屋さんは「宮古島に興味はあっても、博物館はハードルが高いと感じる方もいる。今回のような催しがその解決のきっかけになれば」と語った。
国際博物館の日は、博物館が社会に果たす役割を広く普及啓発するため、1977年にモスクワで開催された国際博物館会議で採択し、毎年5月18日と制定した記念日。日本は02年から日本博物館協会を主体として参加。全国各地で美術館や博物館の無料公開や開館時間の延長、他の博物館との連携事業、地域との連携イベントなどが行われている。