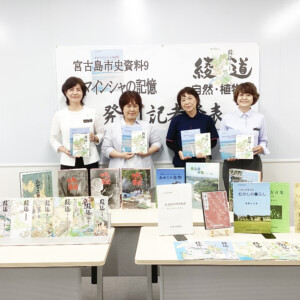当事者から学ぶ若年性認知症 病と向き合う力強いメッセージ 希望大使の大城氏特別講演
若年性認知症家族会「ま~つきずみの会」と宮古島市の共催で若年性認知症の認識拡大と理解促進を目的としたスペシャル講演会が23日、市役所で開かれた。40歳で若年性アルツハイマー病と診断された「沖縄県認知症希望大使」の大城勝史氏が登壇し、自身の経験を基にした講演を行った。会場にはほぼ席が埋まるほどの来場があり、大城氏は「認知症になっても、まだできることがたくさんある。働き続けることができるのもその一つ」と語り、認知症への理解を深めることが社会全体の課題であると訴えた。
若年性認知症とはアルツハイマーなどといった脳の疾患により64歳以下で発症する認知症を指し、国内では10万人に50・9人の当事者がいると言われるが、支援体制にはまた課題もある。
こうした中、認知症について正しく知ってほしいと顔と名前を公表して自らの体験を語った豊見城市出身の大城氏は1974年生まれの現在、50歳。
講演では、大城氏が認知症と診断されるまでの経緯や、診断後の生活、家族や職場との関係について具体的に述べた。また、認知症の偏見に対する問題提起も行い、社会全体でのサポートの必要性を強調した。
大城氏は35歳で不調を感じ病院に行くも原因が分からず、41歳の誕生日前に若年性アルツハイマー病と診断が出るまで、取引先の人の顔を忘れてしまうなど仕事でのたくさんの困難があったことを語った。
また、診断後には自分の子どもたちに父として泣く姿を見せたくなくて、妻に話してもらったことなどを振り返った。
大城氏は「認知症になると、何もかもできなくなるわけではない。各々できることがたくさんあり、周囲の人の力を借りてできることもたくさんある。10年以上続けているブログによって仲間とつながることができ、それが元気につながり、またそのブログを読んで、元気や勇気を自分からもらってくれる人もいる」と語った。
その上で「当事者同士でいろいろな情報や感情を交換したり共有することができることで前向きにもつながった」と述べた。
講演会では大城氏のような当事者の生の声が、若年性認知症に対する社会の偏見を払拭し、当事者や家族が直面する課題に対して、より具体的な支援策を模索するきっかけとなった。