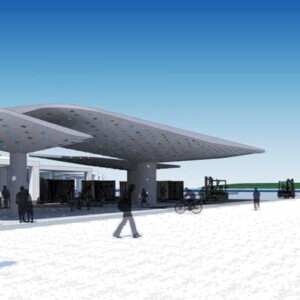発掘が語る“島の時間” 文化講座第4回 久貝氏歴史を地層から紐解く
宮古島市教育委員会の歴史文化活用推進事業・文化講座第4回が23日、市歴史文化資料館で開かれ、同課の久貝弥嗣さんが「発掘調査にみる宮古島市の歴史―グスク時代から沖縄戦」をテーマに解説した。参加者は約13人が。無土器文化の人類痕跡からグスク時代への転換と石積み遺跡、王国期や近代の交易や水中・戦争遺跡まで、最新の発掘成果をもとに島の歴史を地層と資料からたどった。
前半では、ツヅピビスキアブ遺跡などから見つかった1万年前の石器やイノシシの骨を紹介し、無土器期には貝斧(シャコガイ製貝斧)や集石遺構が確認され、海岸段丘上の生活圏や火の使用痕跡が見つかっていることを示した。約300年間の「空白期」を経て、11世紀後半に北(九州・沖縄本島)から流入した文化や人々の動きを人骨、副葬品、6柱建物跡が住屋遺跡で発見されたことを読み解き、外来系の生活様式が宮古に定着したと報告した。
久貝さんは、グスク時代を「12~16世紀にかけて城(グスク)が築かれ、農耕社会が確立した時代」と位置づけ、按司(あじ)と呼ばれる支配者層の出現や農業生産の発展、鉄器・中国陶磁器の流通などを説明した。
その上で福州ルートを通じた南方交易により滑石石鍋や白磁が島にもたらされ、奄美から先島にかけて共通の物質文化が形成されたとした。さらに、13~15世紀に丘陵上へ築かれた石積み遺跡(高腰城跡など)が防御的集落の痕跡であり、与那覇原の騒乱伝承と考古年代が一致することを指摘した。
後半は、琉球王国期の交易と近世以降の考古資料を紹介。漲水港を中心に那覇を結ぶ流通網が整備され、宮古独自の薄手黒艶の「浅鉢」が外交や贈答用の土器として用いられたことを解説した。
また、1771年の明和の大津波(乾隆三十六年大波)による堆積層の保存性や、プロビデンス号やレディー・イブリン号などの水中遺跡、旧西中共同製糖場の煉瓦窯跡なども紹介。市内では現在、200件超の戦争遺跡が確認されており、調査・保存・展示が進められていることも報告した。
久貝さんは「宮古は旧石器から近代まで、断続的ながら連続した人の営みが見える。発掘調査は記憶を掘り起こす作業でもある」と語り、参加者らは地中から浮かび上がる“島の時間”に耳を傾けた。
質疑では、貨幣が宮古へ届きにくかった理由(王府の配分規制と物々交換の継続)や、ドイツ皇帝博愛記念碑の沿革、開発行為と事前調査の連携方法などに関心が集まった。
久貝さんは「現地の発掘・聞き取り・記録保存を積み重ね、展示や学習へ還元していきたい」と語った。