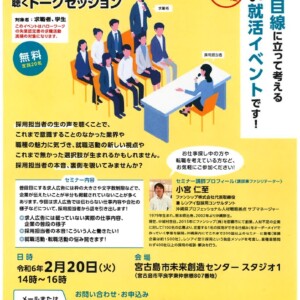宮古芸能に次世代の光を 多角的行動指針を確認 若者参加・施設改善へ提言
宮古島市市制施行20周年記念事業の一環として、来月開催を控える第20回市民総合文化祭の座談会「宮古島市における芸能―その歩みと今、そして未来へ」が27日、未来創造センターで開催された。市文化協会芸能部会や教育長、マスメディア関係者らが参集し、現状課題の整理と継承・発展の方向性について意見交換を行い、市民文化の担い手不足や環境整備の遅れといった現実を踏まえつつ、宮古芸能の継承と発展に向けた多角的な行動指針を確認する場となった。
座談会には宮城克典教育長をはじめ、同文化協会に加盟する芸能部会32団体からの代表、新聞・テレビ・ラジオ各社の関係者が参加。今回主催した同文化協会の饒平名和枝会長が「さまざまな角度から宮古における芸能文化の未来を展望し、豊かで魅力的な宮古の発展につながるようご意見をお願いしたい」と述べた。
議論は「現在の課題」「必要な取り組み」「継承と未来の展望」の3つのテーマに沿って進行された。
そのうち、課題については、加入団体の高齢化や若年層参加の低迷、指導者不足、活動機会の減少などが指摘された。施設面では未来創造センターの音響不全や設備老朽化、舞台運用規程の制約が課題として共有され、改善と予算措置の必要性が訴えられた。
また、県では新聞社主催の積極的な藝能祭の開催がこれまでの発展につながったとして市内での開催を望む声も上がった。
取り組みとしては、学校教育との連携強化や放課後枠の活用、人材バンク制度の見直し、三線など備品の整備を含む提案が示された。
民謡協会関係者は「子どもが民謡に触れる機会が少ない。公民館の放送を活用すべき」と訴え、教育現場からは「総合的な学習などを活用できるかもしれない」との提案があり、クラブ活動復活を望む声も話題に上った。
また現状では選択肢が広がったことやダンスに取り組む子どもたちも増えたことも挙げられ、教育プログラムに盛り込まれる影響の大きさも共有された。
そのほか、「宮古芸能の日」など目的を明確にしたイベント開催や、活動を広く発信するための動画配信など広報戦略の強化も意見に上がった。
未来の展望では「楽しさ」を核に据えた子どもの参加設計や、民謡と舞踊、器楽を組み合わせたコラボ舞台、映像アーカイブによる体系的保存などが提示された。
饒平名会長は「大人がいても学ぶ子どもがいなければ未来を語れない。きょうの意見を基に一歩ずつ前進したい」と締めくくり、宮城教育長も「才能を掘り起こして育て、宮古の文化を盛り上げていきたい」と語った。