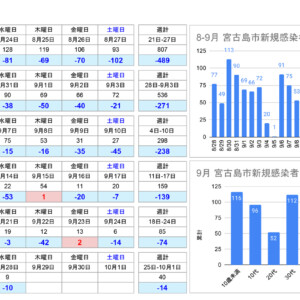宮古島市の合併変遷探る 市立図書館 市制20周年で特別開催
市立図書館は27日、同館内のブラウジングコーナーで2025年度第1回「郷土の歴史と文化講座」と「ライブラリーライブVol.1」として、トークイベント「はじまりの声~宮古島市のスタート~」を開催した。市制20周年の節目に、旧5市町村からの合併を知る関係者3人を招き、名称決定や議会統合、地域意識の変遷などについて、裏話を交えて語った。来場者は当時の出来事に耳を傾けながら、郷土の成り立ちと未来を見つめ直す機会とした。
イベントは、合併当時の思いを象徴する「宮古島市歌~黎明の空に~」の合唱で幕を開けた。進行役の長濱一美さんが案内し、市歌作詞者で元宮古テレビの記者砂川健次さん、長年FMみやこのパーソナリティを務めた與那覇光秀さん(宮原商店代表)、合併当時の2005年宮古青年会議所(JC)理事長の宮里敏彦さんがパネリストとして当時のことを振り返った。
與那覇さんは、当時FMみやこ開局3年目で、合併に向けたカウントダウン放送などを実施した経験を紹介。地域対抗意識が強かった背景や、合併後20年を経て方言や神行事が減少していることへの危機感も述べた。
宮里さんは「宮古島市」という名称決定に至る過程を詳細に解説。岩手県の宮古市は名称使用に賛成だったが、市民の反発を受け、当時の商工会議所と共同で実施した新聞アンケートで「宮古島市」が最多となり決定したと明かした。
また、合併時に存在した議員定数80人問題では、「地域を良くするために議員になったのではないか」と問い直すアンケートをJCで実施し、制度見直しに影響を与えた経緯も説明。宮古まつり復活時には、JCが一時的に豊年祈願祭を引き継いだ逸話も紹介した。
砂川さんは市歌の歌詞について、「2日で完成した。沖縄の文化や宮古各地の特徴が、頭の中で自然と組み合わさってできた」と振り返り、1番から3番それぞれの意味も解説した。
来場者からは「合併時の市役所職員は手続きが大変だったが、皆ワクワクしていた」と当時を振り返る一方で「観光客は増えても暮らしは豊かになったのか」といった意見も寄せられた。
主催者によると、本講座は文化芸術や歴史に触れ、多様な関心を広げる場として今後も継続していく方針とのこと。